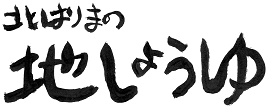昨年からイベント限定で取り組んでいる「播州しょうゆ焼きそば」。当店のお醤油を使って家でやきそばを焼いてお友達に振舞っている方とお話しした事から始まった取り組み。
北播磨地域の食材を使い、この地域の良さ・楽しさ・面白さを焼きそばを通じて伝えたい。そんな思いで少しずつ手伝ってくださる方も増えてきました。

食べてくださる方に「この焼きそばに出会ってよかった!」と思って頂ける、皆で知恵を出し合いながら、味良し・見た目良し・感動良しの素晴らしい焼きそばにしていきます。お祭りで出会った際には、是非食べてみてください!思いを届けることができる焼きそばに向けて頑張るぞ!

帰りのフェリー。小豆島では、元気いっぱい・やる気いっぱい・情熱いっぱいもらって素晴らしい時間を過ごすことができました。フェリーの甲板にあがり、海風に当たっていると何だか、ドッと疲れが。
「よし、夕焼けもキレイだし、風も心地よいし、外でカップラーメンを食べよう!」と

なんだかんだ色々食べた旅のシメが船の中で売っているカップラーメンなせがれでした(^^;



最後に紹介する醤油屋さんは「ヤマサン醤油」です。小豆島視察の一番最後に寄ったお店です。なぜ、立ち寄ろうと思ったのかというと、視察前ピックアップをしていたときに、「食事処」が併設させているのを知ったからです。醤油屋さんが営む食事処って気になりませんか?だから、足を運んでみました。


店内に入って「ご飯まだ食べれますか?」と女将さんに相談すると「大丈夫!」と奥の食事スペースへ。女将さんと共に大将もお店に立たれていました。女将さんが「醤丼(ひしおどん)、めちゃくちゃ美味しいから。一回食べてみて。チャーシューにうちのもろみが合うの。」と醤丼をオススメしてくださったので、注文してみました。

出てきたらこんな丼ぶりでした。「そんなに美味しいの?」と少し半信半疑でしたが、食べてびっくり!メチャメチャ美味しかったんです。美味しさの秘訣が2つありました。①チャーシューにもろみをつけて食べる。②ご飯が醤油でおこげを付けたような香ばしいご飯。です。この2つのポイントの相乗効果で、ペロリと食べてしまいました。
女将さんと大将の強烈なキャラクターに面食らうかもですが、食べ終わり店を出るころには、小豆島でイチバン印象に残った醤油屋さんでした。女将さんの息子さん自慢話がとても面白く、また会いに来たいなぁと思える素晴らしいお店でした。ご飯を食べるところで迷われている方、ヤマサン醤油のチャーシュー醤丼を絶対食べて帰ってください(^^)

小豆島という小さな地域の中に、多くの醤油屋さんがありました。それぞれの個性が違うことで、観光に来られたお客様もたくさん回っても飽きない、醤油が面白く楽しく感じる、そんな素晴らしい小豆島でした。発酵に興味がある方は、絶対に行くべきスポットです。マイカーで島内を動き回れるように行くことをお忘れなく!小豆島視察、最後の投稿でした!

今回が小豆島視察ブログのpart.4。今回は感銘を受けた醤油屋さんをご紹介しようと思います。
今回は『ヤマロク醤油』さんという醤油屋さんです。なぜ、この醤油屋さんに行ったかというのがすべてです。
現在、写真にも写っていますが、こういった大きな木桶を作る職人が全国にほとんど無くなってしまい、各地の醤油メーカーは木桶が経年劣化でダメになると、プラスチックの大きな桶に切り替えていっているのが現状です。しかし、このヤマロク醤油さんの5代目は、自ら木桶作りに取り組むべく、修行に行ったり、地元の大工さんと連携したり、様々な工夫をして、なんとか後世に木桶作りの醤油を残したいと頑張っておられます。



こうした取り組みがテレビなどでも度々取り上げられ、写真にも写っていますが、お店の右側には有名人の指色紙が山のように飾られていました。お店の右側ではスタッフさんが、醤油ラベルの手張り作業を行われていたり、とても開放的で店構えだったので、気軽に入ることが出来ました。


お醤油の種類も数種類のみで、ボトルや容量が違うものの、ヤマロク醤油さんが伝えたい思いがお客様にしっかり伝わるよう、こだわり抜かれた売店でした。
お醤油を眺めていると、スタッフさんが「工場見学もできますが、案内しましょうか?」と声を掛けてくださいました。こだわりの木桶を拝見したかったのもあり案内していただきました。中に入ると・・・


こういった感じでした。いつ頃に建ったのか分からないくらい古い建物だそうで、醤油蔵特有の木の様子が伺えました。実際に五代目が作られた木桶の最初の試作を見せていただき、醤油造りに対する熱い思いを感じました。
醤油造りはこれまでの歴史の上に、今があり、今の取り組みが未来に残す足掛かりとなります。醤油醸造に関わっているすべての人はこの事を理解しているはずですが、実際に行動に起こすには相当の勇気と情熱と根気が必要に違いありません。小豆島という醤油に深く関わる土地で醤油文化を継承していく、そんな素晴らしい景色に出会たヤマロク醤油さんでした。



小豆島の中でビックリするくらい大きな建物があります。大きな工場が何棟も連結して広大な敷地で醤油醸造に取り組んでいるのが「マルキン醤油」さん。福田港から車で20分ほどのところにあります。
醤油造りをどのように始めたのか、現在に至るまでの歴史が見学できるマルキン醤油記念館に行ってきました。当店が取り組んでいる「古式製法」で使用している木製天秤搾り機や麹室が、昔の仕込み方法として展示されていました。


昔、機械を頼らず搾りを行う際はどの醤油蔵でもこういった天秤搾り機でもろみ搾りを行っていました。しかし、石の重みのみでしぼるため、取れ高が少なく、製品にできる量も少なくなってしまうのが難点でした。そこで、水圧でもろみを搾る機械が登場し、カスカスに水分がなくなるまでプレスし、取れ高を多くする流れになりました。しかし、余分な雑味まで出してしまう機械での搾りに比べて、天秤搾り機での搾りは緩いため、お醤油の良いところだけを抽出できるのがストロングポイントだと言えます。

醤油の製法はそれぞれ一長一短です。機械を取り入れることで人件費や労力を節約できるとともに、他の事に労力を割くことができます。しかし、時代の流れに逆らうように機械を使わない昔の製法を大切にすることで、醤油の味と共に大切な何かを伝えることができると思います。
醤油メーカーにはそれぞれの役割があります。世界中のお客様に使っていただける安心安全な醤油を作る、若者向けに発信してこれからの食文化をリノベーションしていきたい、地域のお客様の家庭の味を守り続けたい、など。
それぞれの立場で、立場に合う製法で、役割に合う醤油製品の開発を各社が行ってこそ、これからの日本の食文化の土台を支える「醤油」が残り続けていくに違いありません。これからも当店の役割を果たし続ける覚悟です。